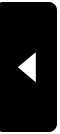ニジマスの燻製作り
唐突だが私は燻製が好きだ。
食材の旨みを引き出す調理法の中でも、燻煙は格別な魅力を持っている。
昔から好きな食べ物も、ベーコン、ソーセージ、スモークサーモン、いぶりがっこ、ウイスキー、ビーフジャーキーなどなど、燻製もしくは燻煙の恩恵を受けた食材が多い。
もともとは食材の保存性を増すために考案された調理法の一つなのだが、燻煙する際に何の煙を用いるかによって食材に付く風味が変わってくる。
今では本来の保存という利用法よりは、どのような風味や味わいを作り出すかといった工夫に主眼が置かれる。
そう、燻製は一つの料理としてのジャンルにまで昇華されているのだ。
漬け込み液のレシピ、漬け込みの時間、塩抜きの時間や乾燥にかける時間、燻煙する際のチップの種類や温度と時間などなど、条件一つで仕上がりも変わってくる。
燻製とは、もはやひとつの芸術であると言っても過言ではない。

燻製には熱燻、温燻、冷燻がある。
・熱燻
80℃以上の高温で燻す方法。
加熱調理も兼ねることができるが保存には向かない。
・温燻
30~70℃の温度で燻す方法。
一般的に燻製といえば温燻を指す。
水分を少なく作れば保存にも向く。
高温にならないように作業するので、冬の間が作成に適する。
・冷燻
30℃以下の低温で1~4週間燻す方法。
生の食材を長期間燻すので設備や管理の手間がかかる。
低温での作業が絶対であるため、空調設備のある施設か冬場の作業になる。
今回作るニジマスの燻製は、温燻である。
手順を簡単に説明すると以下のようになる。
1日目 夜 ソミュール液など、浸け込み液の作成
2日目 朝~ 釣行~下処理
2日目 昼~ ニジマスの漬け込み(12時間程度)
2日目 夜~ 塩抜き(30分)、乾燥(12時間程度)
3日目 昼~ 燻煙(8時間程度)
3日目 夜~ 熟成(半日~1日)
4日目 昼 完成!
お分かりいただけただろうか。
赤で書いてある部分の工程はほったらかしではできないため、最低2日間の連休が無いと作れないのだ。
そう、恐怖の社畜殺しなのである・・・キャァー
では、手順を順番に見ていこう。
<浸け込み液作り>
浸け込み液にはいくつか種類もあり、レシピもさまざまである。
ここでは私流のソミュール液を紹介する。
・水 4L
・砂糖 60g
・塩 350g
・ローリエ 10枚
・ブーケガルニ 3包
・ニンニク 3片 スライス
・鷹の爪 1本 ちぎって
・黒コショウ 適量 ミルで挽いて
・白ワイン 500ml
水4Lを鍋で沸騰させ、白ワイン以外の材料を鍋に入れ、5~10分煮出す。
その後火を止め、冷めたら白ワインを加え、冷蔵保存する。

レシピはあくまで一例であり、ぜひとも各自で創意工夫しておいしいソミュール液を作ってみてほしい。
良いレシピができましたら私にも教えて下さい!
写真に写っている市販のティーバッグ型ブーケガルニは、ゆくゆくは庭で栽培したハーブ類で自作したいと考えている。
ローズマリーやタイム、セージ、パセリ、マジョラム、オレガノ、セロリなど、工夫してみると楽しそうである。
他にも、塩は塩化ナトリウムオンリーの塩よりも海水塩、岩塩、塩田塩の方がおいしく仕上がる。
藻塩(海藻の旨みが溶け込んだ塩)を用いるのが私の最近のブームである。
他には砂糖の代わりにきび糖を用いたり、ワインもフルーティーで美味しいものをチョイスするなど、レシピにこだわらず「これはおいしい」と思える食材があれば積極的に利用したい。
また、私はスパイシーな出来上がりが好きなこともあって、ハーブやコショウを多めに使っている。
よりマイルドな仕上がりが好みならば鷹の爪やハーブ類を減らすなど好みに合わせて調節してもらいたい。


<ニジマスの漬け込み>
さて、ニジマスを釣ってきたら、できるだけ早く下処理を行う。
理想はニジマスが生きているうちに釣り場で済ませ、クーラーボックスで持ち帰ることだ。
鰓を取り腹を割り、内臓を引き抜き、背骨に沿って付いている腎臓をこそげ落とす。
金だわしでこすって鱗を落とし、ぬめりも取る。
以上の下処理を終えたら、良く冷えたソミュール液に漬ける。
しっかり全体が浸かるようにするのが大切である。
あまり大きな容器を使うとソミュール液がいくらあっても足りないので、入れるニジマスのサイズに合わせた容器を用意するといい。



この後、冬場なら日の当らない軒下などに12時間ほど置く。
気温が高くなるときは、冷やした保冷剤を入れたり、容器ごと冷蔵庫に入れるという手もある。
<塩抜き>
せっかく味をしみ込ませたわけなのだが、今度はそれを抜く作業だ。
わざわざ抜くくらいなら最初から薄めに作っておけばいいのではないかと思われるであろう。
なぜそのような二度手間とも思えることをするかというと、実は塩分濃度が高くないと中まで味が浸透しないのだ。
私のレシピでは塩分濃度8%程度である。
漬け込みには最低5%は塩分濃度が無いと味がしみ込まないのだ。
当然、それら中心部分まで味が浸透する濃度ではとてもではないが塩辛くて食べられない。
そういう理由から、一度濃い浸け込み液で浸け、中まで味が浸透したら食べるのに適した濃さにまで塩を抜くのだ。
抜き方は、液をすべて捨て、真水にさらすだけである。
その際に、水道の水を細く絞って水が流れるようにすると均一に塩分が抜ける。
この塩抜きが燻製作りにおいては最も難しいと言っても過言ではない。
慣れないうちは抜きすぎに注意をしてほしい。
塩を抜きすぎた燻製は美味しくないのだ。
自分なりに何度も試してみて、その都度メモを取り、塩分濃度や浸け込み時間、塩抜きの時間の最適と思える時間を割り出してほしい。
<乾燥>
塩抜きが終わったら、水の中で残ったぬめりを軽く取り、水から上げ一匹ずつ布巾で水分をふき取る。
この作業は塩抜きが終わった魚を全部水から上げてから行うようにする。
水に浸けたまま一匹ずつ取り出していたのでは、作業の最初と最後の個体で塩抜き加減が変わってしまうからだ。
必ず清潔な布巾で拭きとり、水分を残さないようにすることがコツである。
ニジマスの数に合わせて布巾もたくさん用意すると良い。
また、キッチンペーパーなどの使い捨てのものを使うのも手だが、思いのほか大量に使うので注意されたい。
表面は勿論、腹の中もきれいにふき取るようにする。
水分をふき取ったら、吊るすためにタコ糸を口に通してゆく。
20cmほどに切ったタコ糸の末端を、背中側から両方のえらに通し、口に抜いたら末端を結ぶ。
その結んでできたループを乾燥や燻煙する際にぶらさげるのに利用する。
乾燥させる際は猫や烏などの動物に取られないように、なおかつ日が当らないような場所がベストである。
12時間程度乾燥させ、全体が透き通ってきて、触ってもベタつかず、身が引き締まった感じになっていれば成功である。

雨の日などは濡れるのを避けて室内で乾燥させるが、乾燥が不十分になることも多い。
そのような時は、扇風機などで風を当てるようにすると良く乾く。
また、許されるならば冷蔵庫内で乾燥させるという手もある。
それでも乾燥が不十分になってしまう場合は、後述の燻煙Aの工程を長めに取るようにすると良い。
<燻煙>
いよいよ燻製におけるメインの工程、燻煙である。
必要な道具はスモークチップやスモークウッドといった燻煙材、それを入れる金属容器、燻製箱、チップを発煙させるための電気コンロ、食材を吊るしたり置いたりする棒やフック、金網などである。
燻煙材
スモークウッド
木材を微粉砕し、棒状に押し固めたもの。
端に点火すると線香のようにくすぶりながら数時間に渡ってゆっくりと燃焼する。
発煙に熱源体を使わないため、低温で燻す用途に適している。
スモークチップ
木材を荒く粉砕したもの。必要量を金属容器に入れ、電気コンロなどの熱源で加熱し、発煙させる。
熱源を用いるので中~高温で燻す用途に適している。

スモークウッドもスモークチップも木材をから出る煙の作用で食材を燻す訳であり、当然用いる樹種の違いにより、食材に付く香りや色合いも違ったものになってくる。
リンゴやクルミ、ナラ、ブナ、サクラなどの樹種が燻製にはメジャーで良く利用されている。
しかし樹木ならば臭いが不快でないものや毒が無い種類であれば何でも使える。
いろいろと試してみて好みの香りが付く樹種を探してみるのも楽しそうである。
ニジマスを燻製にする上でぜひオススメしたいのがヒッコリーである。
アメリカ原産のクルミ科Carya属の樹木数種を指してヒッコリーと呼んでいる。
ペカンナッツのペカンもヒッコリーである。
燻製にした際の色付きも良く、風味もとても良いので、樹種に悩んだら使ってみてほしい。
燻製箱
特別なものを用意しなくても、段ボールなどで作ることもできる。
段ボールを用いての燻製箱作りは多くのサイトで紹介されているのでそちらを参照されたし。
私は燻製作りの度に燻製箱を作るのが面倒だったので、長く使える燻製箱を木材でDIYして作ることにした。



お金をかけて高級品を作る気も無かったので、SPF1×4材製である。
サイズはW483×D712×H800mm
総額5000円弱。
難点は、重い!ことである。
内部の温度が安定しやすいようにと大きめに制作したのだが、それが仇となりかなり重くなってしまった。
材料をそろえる段階で薄々とは気付いていたのではあるが、気付かないふりをして作り上げてしまったのだ。
これはもう、腰に深刻なダメージを与えるレベルである。
取っ手の取り付けのヤケクソ感や、扉のナナメ感がじわじわくる仕上がりになってしまったので作りなおそうかとも思ったのだが、やはり面倒なのでそのまま使うこととした。
<燻煙>
温燻を作るにあたっての手順は以下の3段階。
A 30℃以下で1~2時間
B 40~50℃で4~5時間
C 60~70℃で1~2時間
ニジマスのサイズや乾燥の具合などで時間は前後するので、様子を見ながら各段の時間は調節する。
雨天などで乾燥が不十分だった場合はAを2時間位と長めに行うが、乾燥が十分であるならばAは1時間にする、といった具合である。
ここにある時間にとらわれることなくいろいろと試してみてほしい。
なお、Aはスモークウッド、B、Cはスモークチップで行う方が温度管理が容易である。
また、B、Cにおいてはゆっくりと温度上昇させるように注意したい。
急激な温度上昇は生焼けっぽくなるなどの失敗の原因となる。
Cにおいては70℃を超えないように注意が必要である。
燻製用の温度計には80℃以上が熱燻と書いてあるものもあるが、70度を超えると熱燻のようになってしまう。
せっかく手間暇かけて温燻を作るのであるから特に注意したい。
温度が上がり過ぎた場合は電気コンロの電源を切るなどで対応する。

スモークウッドを用いる際は、写真のように金属トレーに金網を敷いたものの上に置くようにすると立ち消えを防止することができるのでオススメである。

B、Cの工程においてチップを利用する際は、写真のように金属容器にチップを入れ、電気コンロで熱して煙を出すようにする。アルミなどの薄い容器はすぐに穴が空いてしまうので小型の鉄フライパンなどが使いやすい。
チップは量にもよるが20~30分ほどで燃え尽きてしまう。
燻製箱から煙が出なくなったら燃えカスを捨て、新たなチップを入れるようにする。
その際にはくれぐれも火事に気をつけたい。
見た目に炎が出ていなくても消し炭の中心部は燃えている場合が多いので確実に消化するようにする。
燻煙が完了するまで何度もチップを交換しなくてはならないが、手間暇かけただけおいしい燻製に仕上がると思えば苦にならないものである。
仕上がりを想像しながら頑張ってもらいたい。
また、ニジマスから油が滴るほど出てしまう場合には、煙の乗りが悪くなったり、脂臭くなったりすることがあるので途中で様子を確認し、キッチンペーパーなどで拭き取るようにすると良い。
熟成
燻煙が終わり、いよいよ完成!早速味わいたいところではあるが、完成直後は煙の刺激的な臭いやえぐさが立っており、美味しく仕上がったとは言い難い。
最後の工程として半日から1日程度空気にさらす熟成が必要である。
ネットなどに入れ外で干しても良いのだが、燻製の香りが気にならないのであれば埃などを防ぐために紙などをかけ、室内に置いておいても良い。

味わう
待ちに待った燻製の完成である。
そのまま皮をむき、味わうのもよし、料理の材料として楽しむのもよし。
おいしい食べ方を探してみてほしい。
私のオススメしたい食べ方はやはりそのまま食すことである。
燻製の香りというものは実に多くの成分を含んでいるようで、ちびりとかじり、ゆっくりとかみしめていると、実に様々な表情を見せてくれるのだ。
時に荒く武骨に、時に繊細に優雅に、時にノスタルジーを感じさせ、時に森を渡る風や渓流の水飛沫を彷彿とさせる。
その味わいの一時は、ニジマスの成長の時間の凝縮であり、燻した樹木が何十年もかけて成長した時間の凝縮であり、その先にあったであろう壮大な生物の進化と淘汰の歴史の凝縮なのである。
燻製という楽しみ、暫くはやめられそうにないな。
イイネ!と思ったらポチしてもらえると嬉しいです

食材の旨みを引き出す調理法の中でも、燻煙は格別な魅力を持っている。
昔から好きな食べ物も、ベーコン、ソーセージ、スモークサーモン、いぶりがっこ、ウイスキー、ビーフジャーキーなどなど、燻製もしくは燻煙の恩恵を受けた食材が多い。
もともとは食材の保存性を増すために考案された調理法の一つなのだが、燻煙する際に何の煙を用いるかによって食材に付く風味が変わってくる。
今では本来の保存という利用法よりは、どのような風味や味わいを作り出すかといった工夫に主眼が置かれる。
そう、燻製は一つの料理としてのジャンルにまで昇華されているのだ。
漬け込み液のレシピ、漬け込みの時間、塩抜きの時間や乾燥にかける時間、燻煙する際のチップの種類や温度と時間などなど、条件一つで仕上がりも変わってくる。
燻製とは、もはやひとつの芸術であると言っても過言ではない。

ニジマスの燻製 おいしそ~~~
燻製には熱燻、温燻、冷燻がある。
・熱燻
80℃以上の高温で燻す方法。
加熱調理も兼ねることができるが保存には向かない。
・温燻
30~70℃の温度で燻す方法。
一般的に燻製といえば温燻を指す。
水分を少なく作れば保存にも向く。
高温にならないように作業するので、冬の間が作成に適する。
・冷燻
30℃以下の低温で1~4週間燻す方法。
生の食材を長期間燻すので設備や管理の手間がかかる。
低温での作業が絶対であるため、空調設備のある施設か冬場の作業になる。
今回作るニジマスの燻製は、温燻である。
手順を簡単に説明すると以下のようになる。
1日目 夜 ソミュール液など、浸け込み液の作成
2日目 朝~ 釣行~下処理
2日目 昼~ ニジマスの漬け込み(12時間程度)
2日目 夜~ 塩抜き(30分)、乾燥(12時間程度)
3日目 昼~ 燻煙(8時間程度)
3日目 夜~ 熟成(半日~1日)
4日目 昼 完成!
お分かりいただけただろうか。
赤で書いてある部分の工程はほったらかしではできないため、最低2日間の連休が無いと作れないのだ。
そう、恐怖の社畜殺しなのである・・・キャァー
では、手順を順番に見ていこう。
<浸け込み液作り>
浸け込み液にはいくつか種類もあり、レシピもさまざまである。
ここでは私流のソミュール液を紹介する。
・水 4L
・砂糖 60g
・塩 350g
・ローリエ 10枚
・ブーケガルニ 3包
・ニンニク 3片 スライス
・鷹の爪 1本 ちぎって
・黒コショウ 適量 ミルで挽いて
・白ワイン 500ml
水4Lを鍋で沸騰させ、白ワイン以外の材料を鍋に入れ、5~10分煮出す。
その後火を止め、冷めたら白ワインを加え、冷蔵保存する。

こんな感じ
レシピはあくまで一例であり、ぜひとも各自で創意工夫しておいしいソミュール液を作ってみてほしい。
良いレシピができましたら私にも教えて下さい!
写真に写っている市販のティーバッグ型ブーケガルニは、ゆくゆくは庭で栽培したハーブ類で自作したいと考えている。
ローズマリーやタイム、セージ、パセリ、マジョラム、オレガノ、セロリなど、工夫してみると楽しそうである。
他にも、塩は塩化ナトリウムオンリーの塩よりも海水塩、岩塩、塩田塩の方がおいしく仕上がる。
藻塩(海藻の旨みが溶け込んだ塩)を用いるのが私の最近のブームである。
他には砂糖の代わりにきび糖を用いたり、ワインもフルーティーで美味しいものをチョイスするなど、レシピにこだわらず「これはおいしい」と思える食材があれば積極的に利用したい。
また、私はスパイシーな出来上がりが好きなこともあって、ハーブやコショウを多めに使っている。
よりマイルドな仕上がりが好みならば鷹の爪やハーブ類を減らすなど好みに合わせて調節してもらいたい。


<ニジマスの漬け込み>
さて、ニジマスを釣ってきたら、できるだけ早く下処理を行う。
理想はニジマスが生きているうちに釣り場で済ませ、クーラーボックスで持ち帰ることだ。
鰓を取り腹を割り、内臓を引き抜き、背骨に沿って付いている腎臓をこそげ落とす。
金だわしでこすって鱗を落とし、ぬめりも取る。
以上の下処理を終えたら、良く冷えたソミュール液に漬ける。
しっかり全体が浸かるようにするのが大切である。
あまり大きな容器を使うとソミュール液がいくらあっても足りないので、入れるニジマスのサイズに合わせた容器を用意するといい。

下処理を終えたニジマス

しっかり全体を浸す 浮いてこないように腹の空気を出しておく

ローズマリーを少し揉んで入れてみた 一気に高級感が増す
この後、冬場なら日の当らない軒下などに12時間ほど置く。
気温が高くなるときは、冷やした保冷剤を入れたり、容器ごと冷蔵庫に入れるという手もある。
<塩抜き>
せっかく味をしみ込ませたわけなのだが、今度はそれを抜く作業だ。
わざわざ抜くくらいなら最初から薄めに作っておけばいいのではないかと思われるであろう。
なぜそのような二度手間とも思えることをするかというと、実は塩分濃度が高くないと中まで味が浸透しないのだ。
私のレシピでは塩分濃度8%程度である。
漬け込みには最低5%は塩分濃度が無いと味がしみ込まないのだ。
当然、それら中心部分まで味が浸透する濃度ではとてもではないが塩辛くて食べられない。
そういう理由から、一度濃い浸け込み液で浸け、中まで味が浸透したら食べるのに適した濃さにまで塩を抜くのだ。
抜き方は、液をすべて捨て、真水にさらすだけである。
その際に、水道の水を細く絞って水が流れるようにすると均一に塩分が抜ける。
この塩抜きが燻製作りにおいては最も難しいと言っても過言ではない。
慣れないうちは抜きすぎに注意をしてほしい。
塩を抜きすぎた燻製は美味しくないのだ。
自分なりに何度も試してみて、その都度メモを取り、塩分濃度や浸け込み時間、塩抜きの時間の最適と思える時間を割り出してほしい。
<乾燥>
塩抜きが終わったら、水の中で残ったぬめりを軽く取り、水から上げ一匹ずつ布巾で水分をふき取る。
この作業は塩抜きが終わった魚を全部水から上げてから行うようにする。
水に浸けたまま一匹ずつ取り出していたのでは、作業の最初と最後の個体で塩抜き加減が変わってしまうからだ。
必ず清潔な布巾で拭きとり、水分を残さないようにすることがコツである。
ニジマスの数に合わせて布巾もたくさん用意すると良い。
また、キッチンペーパーなどの使い捨てのものを使うのも手だが、思いのほか大量に使うので注意されたい。
表面は勿論、腹の中もきれいにふき取るようにする。
水分をふき取ったら、吊るすためにタコ糸を口に通してゆく。
20cmほどに切ったタコ糸の末端を、背中側から両方のえらに通し、口に抜いたら末端を結ぶ。
その結んでできたループを乾燥や燻煙する際にぶらさげるのに利用する。
乾燥させる際は猫や烏などの動物に取られないように、なおかつ日が当らないような場所がベストである。
12時間程度乾燥させ、全体が透き通ってきて、触ってもベタつかず、身が引き締まった感じになっていれば成功である。

こんな感じ
雨の日などは濡れるのを避けて室内で乾燥させるが、乾燥が不十分になることも多い。
そのような時は、扇風機などで風を当てるようにすると良く乾く。
また、許されるならば冷蔵庫内で乾燥させるという手もある。
それでも乾燥が不十分になってしまう場合は、後述の燻煙Aの工程を長めに取るようにすると良い。
<燻煙>
いよいよ燻製におけるメインの工程、燻煙である。
必要な道具はスモークチップやスモークウッドといった燻煙材、それを入れる金属容器、燻製箱、チップを発煙させるための電気コンロ、食材を吊るしたり置いたりする棒やフック、金網などである。
燻煙材
スモークウッド
木材を微粉砕し、棒状に押し固めたもの。
端に点火すると線香のようにくすぶりながら数時間に渡ってゆっくりと燃焼する。
発煙に熱源体を使わないため、低温で燻す用途に適している。
スモークチップ
木材を荒く粉砕したもの。必要量を金属容器に入れ、電気コンロなどの熱源で加熱し、発煙させる。
熱源を用いるので中~高温で燻す用途に適している。

スモークウッドとスモークチップ
スモークウッドもスモークチップも木材をから出る煙の作用で食材を燻す訳であり、当然用いる樹種の違いにより、食材に付く香りや色合いも違ったものになってくる。
リンゴやクルミ、ナラ、ブナ、サクラなどの樹種が燻製にはメジャーで良く利用されている。
しかし樹木ならば臭いが不快でないものや毒が無い種類であれば何でも使える。
いろいろと試してみて好みの香りが付く樹種を探してみるのも楽しそうである。
ニジマスを燻製にする上でぜひオススメしたいのがヒッコリーである。
アメリカ原産のクルミ科Carya属の樹木数種を指してヒッコリーと呼んでいる。
ペカンナッツのペカンもヒッコリーである。
燻製にした際の色付きも良く、風味もとても良いので、樹種に悩んだら使ってみてほしい。
燻製箱
特別なものを用意しなくても、段ボールなどで作ることもできる。
段ボールを用いての燻製箱作りは多くのサイトで紹介されているのでそちらを参照されたし。
私は燻製作りの度に燻製箱を作るのが面倒だったので、長く使える燻製箱を木材でDIYして作ることにした。

完成直後 前面からの雄姿

背面 3つのぽちは排煙の穴をコルク栓で塞いだもの

前面の扉を開け、機材をセッティング
お金をかけて高級品を作る気も無かったので、SPF1×4材製である。
サイズはW483×D712×H800mm
総額5000円弱。
難点は、重い!ことである。
内部の温度が安定しやすいようにと大きめに制作したのだが、それが仇となりかなり重くなってしまった。
材料をそろえる段階で薄々とは気付いていたのではあるが、気付かないふりをして作り上げてしまったのだ。
これはもう、腰に深刻なダメージを与えるレベルである。
取っ手の取り付けのヤケクソ感や、扉のナナメ感がじわじわくる仕上がりになってしまったので作りなおそうかとも思ったのだが、やはり面倒なのでそのまま使うこととした。
<燻煙>
温燻を作るにあたっての手順は以下の3段階。
A 30℃以下で1~2時間
B 40~50℃で4~5時間
C 60~70℃で1~2時間
ニジマスのサイズや乾燥の具合などで時間は前後するので、様子を見ながら各段の時間は調節する。
雨天などで乾燥が不十分だった場合はAを2時間位と長めに行うが、乾燥が十分であるならばAは1時間にする、といった具合である。
ここにある時間にとらわれることなくいろいろと試してみてほしい。
なお、Aはスモークウッド、B、Cはスモークチップで行う方が温度管理が容易である。
また、B、Cにおいてはゆっくりと温度上昇させるように注意したい。
急激な温度上昇は生焼けっぽくなるなどの失敗の原因となる。
Cにおいては70℃を超えないように注意が必要である。
燻製用の温度計には80℃以上が熱燻と書いてあるものもあるが、70度を超えると熱燻のようになってしまう。
せっかく手間暇かけて温燻を作るのであるから特に注意したい。
温度が上がり過ぎた場合は電気コンロの電源を切るなどで対応する。

スモークウッドを用いる際は、写真のように金属トレーに金網を敷いたものの上に置くようにすると立ち消えを防止することができるのでオススメである。

B、Cの工程においてチップを利用する際は、写真のように金属容器にチップを入れ、電気コンロで熱して煙を出すようにする。アルミなどの薄い容器はすぐに穴が空いてしまうので小型の鉄フライパンなどが使いやすい。
チップは量にもよるが20~30分ほどで燃え尽きてしまう。
燻製箱から煙が出なくなったら燃えカスを捨て、新たなチップを入れるようにする。
その際にはくれぐれも火事に気をつけたい。
見た目に炎が出ていなくても消し炭の中心部は燃えている場合が多いので確実に消化するようにする。
燻煙が完了するまで何度もチップを交換しなくてはならないが、手間暇かけただけおいしい燻製に仕上がると思えば苦にならないものである。
仕上がりを想像しながら頑張ってもらいたい。
また、ニジマスから油が滴るほど出てしまう場合には、煙の乗りが悪くなったり、脂臭くなったりすることがあるので途中で様子を確認し、キッチンペーパーなどで拭き取るようにすると良い。
熟成
燻煙が終わり、いよいよ完成!早速味わいたいところではあるが、完成直後は煙の刺激的な臭いやえぐさが立っており、美味しく仕上がったとは言い難い。
最後の工程として半日から1日程度空気にさらす熟成が必要である。
ネットなどに入れ外で干しても良いのだが、燻製の香りが気にならないのであれば埃などを防ぐために紙などをかけ、室内に置いておいても良い。

燻煙完了 あとは熟成を待つのみ
味わう
待ちに待った燻製の完成である。
そのまま皮をむき、味わうのもよし、料理の材料として楽しむのもよし。
おいしい食べ方を探してみてほしい。
私のオススメしたい食べ方はやはりそのまま食すことである。
燻製の香りというものは実に多くの成分を含んでいるようで、ちびりとかじり、ゆっくりとかみしめていると、実に様々な表情を見せてくれるのだ。
時に荒く武骨に、時に繊細に優雅に、時にノスタルジーを感じさせ、時に森を渡る風や渓流の水飛沫を彷彿とさせる。
その味わいの一時は、ニジマスの成長の時間の凝縮であり、燻した樹木が何十年もかけて成長した時間の凝縮であり、その先にあったであろう壮大な生物の進化と淘汰の歴史の凝縮なのである。
燻製という楽しみ、暫くはやめられそうにないな。
イイネ!と思ったらポチしてもらえると嬉しいです
Posted by アルマス at │Comments(0)
│燻製作り