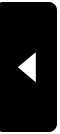ブルーバックレインボーを求めて
10月3日
野反湖という湖には、背中の青いニジマス、ブルーバックレインボーが生息している。
いつ、どこで知った記憶であったかは既に忘れてしまったが、そんなニジマスがいるのならばぜひこの手で釣ってみたいという思いがあった。
しかし、その思いも日々の生活に揉まれ流され、今年を迎えるまでは記憶の深淵へと沈殿してしまっていた。
今年の4月に成田にある管理釣り場、ジョイバレーを訪れた際の事である。
ドナルドソンを掛け、ファイトの末マッディウォーターから浮かび上がったその背中は、息を呑むような青色であった。
その時に野反湖のブルーバックレインボーの記憶も一緒に釣り揚げられるに至り、ひっそりと釣行の計画を立てていたのだ。
場所は群馬県 新潟県や長野県との県境近くの山上湖である。
亜高山帯に位置するため、夏でも水温が低く、真夏であってもトラウトフィッシングが楽しめるフィールドとして有名である。
湖畔にはキャンプ場やコテージなどの施設があり、休日には多くの人が訪れるようである。
せっかく遠出をするのだから大いに満喫しようと考え、キャンプをして2日間釣りをすることにした。
カーナビで所要時間を確認すると、約4時間。
ここ最近の日の出は4:30頃なので、0時に出発すれば朝マズメに間に合いそうである。
高速を抜け、山道をひた走り、夜間で道が空いていたこともあり3:30頃には到着してしまった。
途中の山道ではタヌキが栗を拾って食べているところに遭遇するなど、割と生き物の姿も見られた。
車を降りるとまだ夜というか真夜中であり、陽が昇る気配は無い。
灯りが全く無い山中なので、街中とは違い星がきれいに見える。
とりあえず券売機で遊漁券を買い、トイレの明かりに来ている昆虫を採集する。
ヒメヤママユがたくさん飛来しており、秋の深まりを感じる。
しばし休憩していると、薄らと東の空が白んできた。
タックルを準備し、ダムの方へと降りていく。
しばらく歩くと眼前に、日の出前の美しい野反湖が広がった。

秋まっただ中にある野反湖の朝は、澄み渡った空気が凛と冷え、荘厳な美しさを放っている。
全く風が無いため、水面は鏡面のようになめらかに澄み、白んだ橙色から濃紺へのグラデーションを映し込む。
滲み込むような寒さに身をすくめながら空と水の接点を眺めていると、まるでパラレルワールドの入口に立っているかのような、そんな錯覚に襲われる。
ダムの上から水面まではかなりの距離があるので、アプローチは難しい。
降りられそうな場所は無いかと上から眺めていると、キャンプ場側に岸まで降りられそうな場所があった。
岸辺に立ってみると、ダムの上からでは気付かなかったが小さな魚がポツリポツリと水面に落ちた虫を食べているのが見える。
水は澄み渡り、岸辺を群れで泳ぐニジマスの稚魚の姿も見えるが、釣れそうなサイズの魚影は見えない。
そうこうしているうちに陽が昇ってきた。
日の出を迎えると、そこかしこにライズが見られるようになってきた。
見えないものの、かなり魚影は濃いようである。
早速スプーンを何投かするも、魚からの反応は得られない。
色を変え、サイズを変え、タダ巻き、巻き下げ、巻き上げ、表層バジング、リフト&フォール、トゥイッチ、ジャーキングと試すもショートバイトすら無い。
これは完全にスプーンを意識していないパターンである。
有名ポイントなのでスレているとは聞いてはいたが、ここまでとは思わなかったというのが正直なところである。
水面の虫には積極的にライズしているので表層虫ルアーなら食わせられる思うのだが、何と虫系ルアーは車の中に置いてきてしまった事に気付く。
いまさら取りに戻るのも億劫であったため、しばらく続けるもののノーフィッシュで終わった。
岸辺を歩いてゆくと、よく釣れるというニシブタワンドに到着した。
陽はだいぶ高くなり、気温もそれに合わせて上がってきたようである。
この辺一帯、特にワンド奥からの眺めは素晴らしいの一言であった。


両脇を尾根に囲まれ、その先には美しい野反湖と、紅葉をたたえた斜面林を一望することができる。
まるで俗世界から隔離され、自分しかいない世界で釣りをしているかのような、そんな錯覚に陥ってしまう。
フライマンが1名先行していたので、挨拶がてら釣果を尋ねると釣れていないとの事である。
フライで釣れないとなると相当厳しい釣りになりそうである。
まぁ聞かなかったことにしてさらに200m程奥に進み、スプーンをキャストする。
4.2gから0.9gまで、ひとしきりのサイズ、カラーで試してみるがバイトが無い。
というか、魚の気配が無い。
朝マズメの食事タイムを終え、深場へと移動してしまったのであろうか?
美しい風景を十分に堪能し、次のポイントへと移動することにした。
ニシブタワンドから先は岸辺が歩けなかったため、山の中を歩いて先を目指す。
しばらく歩くとキャンプサイトが見えてきた。
なるほど今日宿泊するキャンプサイトはここか、と確認しつつ岸辺へ降りられる場所を探す。
キャンプサイト奥にけもの道のようなトレイルがあり、その先が湖畔に繋がっていた。
地図で確認すると、テン場下という場所のようだ。
ここは流れもあり沖の方はかなりの水深がある。
そのため、大型個体の回遊がみられるポイントとなっているようだ。
4.2gのスプーンをキャストしボトムの様子を探ってみると、岸辺から20~30m辺りまでシャローで、その先が急峻なブレイクになっているようである。
このような沖に急なブレイクがある場合、その先のボトム付近を攻めるとラインが根ずれし、最悪根掛かりしてしまう。
遠投後着水からテンションフォールでブレイクラインすれすれを通し、ブレイクラインに沿って回遊してくる個体を狙うことにする。
しかしなかなかヒットしない。
そもそも回遊待ちのようなスタイルの釣りは好きではないのでそろそろ移動しようかと考えていた矢先、大きく明確なバイトがロッドを伝ってきた。
即合わせると、ブレイクライン上でそれは大きく飛び跳ねた。
おおお、でかい!
50cmはあろうかという個体が水飛沫を上げ、何度もジャンプする。
飛び跳ね、ラインから逃れるため左右に猛スピードで走り回る。
ネイティブ個体は管釣りと比べて格段に元気が良いとは聞いてはいたが、ここまでとは思わなかった。
ネイティブトラウトに傾倒する諸兄の気持ちがよく分かる。
近くまで寄せ、その魚体を確認すると、何と背中が青いではないか。
ブルーバックだ!
浅瀬まで寄せてもなお勢いよく走り続けるその背中は、まるで水中を往来するカワセミのようである。
頭を水上に浮かせたところをランディングネットで取り込む。
ホウライマスのように白銀に輝く43cmのニジマスであった。


鰭が再生しきっていないので、放流後あまり時間のたっていない個体と思われる。
しかしながら野反湖の自然にもまれ、体力は大幅に回復していることはファイトからうかがえた。
陸に揚げ、まじまじと背中を見るも特に青いという印象は受けない。
ファイト中に見た、息をのむような青はどこへ行ってしまったのだろうか。

おそらく水中にいる時には青く見えるというものなのであろう。
ニジマスは青い水槽で飼育すると白色、銀色化するという科学論文もある。
おそらくは野反湖の澄みきった水は青色の波長をよく通すので、湖底は青色をしているはずである。
そのような環境で育ったニジマスはニジマス特有の色素を多く失い、白銀化し、青色波長の透過率も高いことから相乗的に青く見えるようになったのであろう、と勝手に推測してみる。
この後、天気が急変し、濃霧に加え強風と横殴りの雨に見舞われた。
さすがは山の天気である。
テントを設営し、回復を待つも一向に回復の兆しが見えないため、残念だが納竿とした。
野反湖で生まれ育ちブルーバックレインボーとなった個体ではなかったものの、大いに楽しませてもらうことができた。
釣った個体はキープし、キャンプの夕食に花を添えてもらうことにした。
*******本日の釣果*******
ニジマス 1匹(43cm)
タックル
ロッド カーディフ NX S72L
リール ストラディックCI4+C2500HGS
ライン スーパートラウト アドバンス4lb
ルアー MIU4.2g オレ金/金
イイネ!と思ったらポチしてもらえると嬉しいです

野反湖という湖には、背中の青いニジマス、ブルーバックレインボーが生息している。
いつ、どこで知った記憶であったかは既に忘れてしまったが、そんなニジマスがいるのならばぜひこの手で釣ってみたいという思いがあった。
しかし、その思いも日々の生活に揉まれ流され、今年を迎えるまでは記憶の深淵へと沈殿してしまっていた。
今年の4月に成田にある管理釣り場、ジョイバレーを訪れた際の事である。
ドナルドソンを掛け、ファイトの末マッディウォーターから浮かび上がったその背中は、息を呑むような青色であった。
その時に野反湖のブルーバックレインボーの記憶も一緒に釣り揚げられるに至り、ひっそりと釣行の計画を立てていたのだ。
場所は群馬県 新潟県や長野県との県境近くの山上湖である。
亜高山帯に位置するため、夏でも水温が低く、真夏であってもトラウトフィッシングが楽しめるフィールドとして有名である。
湖畔にはキャンプ場やコテージなどの施設があり、休日には多くの人が訪れるようである。
せっかく遠出をするのだから大いに満喫しようと考え、キャンプをして2日間釣りをすることにした。
カーナビで所要時間を確認すると、約4時間。
ここ最近の日の出は4:30頃なので、0時に出発すれば朝マズメに間に合いそうである。
高速を抜け、山道をひた走り、夜間で道が空いていたこともあり3:30頃には到着してしまった。
途中の山道ではタヌキが栗を拾って食べているところに遭遇するなど、割と生き物の姿も見られた。
車を降りるとまだ夜というか真夜中であり、陽が昇る気配は無い。
灯りが全く無い山中なので、街中とは違い星がきれいに見える。
とりあえず券売機で遊漁券を買い、トイレの明かりに来ている昆虫を採集する。
ヒメヤママユがたくさん飛来しており、秋の深まりを感じる。
しばし休憩していると、薄らと東の空が白んできた。
タックルを準備し、ダムの方へと降りていく。
しばらく歩くと眼前に、日の出前の美しい野反湖が広がった。

秋まっただ中にある野反湖の朝は、澄み渡った空気が凛と冷え、荘厳な美しさを放っている。
全く風が無いため、水面は鏡面のようになめらかに澄み、白んだ橙色から濃紺へのグラデーションを映し込む。
滲み込むような寒さに身をすくめながら空と水の接点を眺めていると、まるでパラレルワールドの入口に立っているかのような、そんな錯覚に襲われる。
ダムの上から水面まではかなりの距離があるので、アプローチは難しい。
降りられそうな場所は無いかと上から眺めていると、キャンプ場側に岸まで降りられそうな場所があった。
岸辺に立ってみると、ダムの上からでは気付かなかったが小さな魚がポツリポツリと水面に落ちた虫を食べているのが見える。
水は澄み渡り、岸辺を群れで泳ぐニジマスの稚魚の姿も見えるが、釣れそうなサイズの魚影は見えない。
そうこうしているうちに陽が昇ってきた。
日の出を迎えると、そこかしこにライズが見られるようになってきた。
見えないものの、かなり魚影は濃いようである。
早速スプーンを何投かするも、魚からの反応は得られない。
色を変え、サイズを変え、タダ巻き、巻き下げ、巻き上げ、表層バジング、リフト&フォール、トゥイッチ、ジャーキングと試すもショートバイトすら無い。
これは完全にスプーンを意識していないパターンである。
有名ポイントなのでスレているとは聞いてはいたが、ここまでとは思わなかったというのが正直なところである。
水面の虫には積極的にライズしているので表層虫ルアーなら食わせられる思うのだが、何と虫系ルアーは車の中に置いてきてしまった事に気付く。
いまさら取りに戻るのも億劫であったため、しばらく続けるもののノーフィッシュで終わった。
岸辺を歩いてゆくと、よく釣れるというニシブタワンドに到着した。
陽はだいぶ高くなり、気温もそれに合わせて上がってきたようである。
この辺一帯、特にワンド奥からの眺めは素晴らしいの一言であった。


両脇を尾根に囲まれ、その先には美しい野反湖と、紅葉をたたえた斜面林を一望することができる。
まるで俗世界から隔離され、自分しかいない世界で釣りをしているかのような、そんな錯覚に陥ってしまう。
フライマンが1名先行していたので、挨拶がてら釣果を尋ねると釣れていないとの事である。
フライで釣れないとなると相当厳しい釣りになりそうである。
まぁ聞かなかったことにしてさらに200m程奥に進み、スプーンをキャストする。
4.2gから0.9gまで、ひとしきりのサイズ、カラーで試してみるがバイトが無い。
というか、魚の気配が無い。
朝マズメの食事タイムを終え、深場へと移動してしまったのであろうか?
美しい風景を十分に堪能し、次のポイントへと移動することにした。
ニシブタワンドから先は岸辺が歩けなかったため、山の中を歩いて先を目指す。
しばらく歩くとキャンプサイトが見えてきた。
なるほど今日宿泊するキャンプサイトはここか、と確認しつつ岸辺へ降りられる場所を探す。
キャンプサイト奥にけもの道のようなトレイルがあり、その先が湖畔に繋がっていた。
地図で確認すると、テン場下という場所のようだ。
ここは流れもあり沖の方はかなりの水深がある。
そのため、大型個体の回遊がみられるポイントとなっているようだ。
4.2gのスプーンをキャストしボトムの様子を探ってみると、岸辺から20~30m辺りまでシャローで、その先が急峻なブレイクになっているようである。
このような沖に急なブレイクがある場合、その先のボトム付近を攻めるとラインが根ずれし、最悪根掛かりしてしまう。
遠投後着水からテンションフォールでブレイクラインすれすれを通し、ブレイクラインに沿って回遊してくる個体を狙うことにする。
しかしなかなかヒットしない。
そもそも回遊待ちのようなスタイルの釣りは好きではないのでそろそろ移動しようかと考えていた矢先、大きく明確なバイトがロッドを伝ってきた。
即合わせると、ブレイクライン上でそれは大きく飛び跳ねた。
おおお、でかい!
50cmはあろうかという個体が水飛沫を上げ、何度もジャンプする。
飛び跳ね、ラインから逃れるため左右に猛スピードで走り回る。
ネイティブ個体は管釣りと比べて格段に元気が良いとは聞いてはいたが、ここまでとは思わなかった。
ネイティブトラウトに傾倒する諸兄の気持ちがよく分かる。
近くまで寄せ、その魚体を確認すると、何と背中が青いではないか。
ブルーバックだ!
浅瀬まで寄せてもなお勢いよく走り続けるその背中は、まるで水中を往来するカワセミのようである。
頭を水上に浮かせたところをランディングネットで取り込む。
ホウライマスのように白銀に輝く43cmのニジマスであった。


鰭が再生しきっていないので、放流後あまり時間のたっていない個体と思われる。
しかしながら野反湖の自然にもまれ、体力は大幅に回復していることはファイトからうかがえた。
陸に揚げ、まじまじと背中を見るも特に青いという印象は受けない。
ファイト中に見た、息をのむような青はどこへ行ってしまったのだろうか。

おそらく水中にいる時には青く見えるというものなのであろう。
ニジマスは青い水槽で飼育すると白色、銀色化するという科学論文もある。
おそらくは野反湖の澄みきった水は青色の波長をよく通すので、湖底は青色をしているはずである。
そのような環境で育ったニジマスはニジマス特有の色素を多く失い、白銀化し、青色波長の透過率も高いことから相乗的に青く見えるようになったのであろう、と勝手に推測してみる。
この後、天気が急変し、濃霧に加え強風と横殴りの雨に見舞われた。
さすがは山の天気である。
テントを設営し、回復を待つも一向に回復の兆しが見えないため、残念だが納竿とした。
野反湖で生まれ育ちブルーバックレインボーとなった個体ではなかったものの、大いに楽しませてもらうことができた。
釣った個体はキープし、キャンプの夕食に花を添えてもらうことにした。
*******本日の釣果*******
ニジマス 1匹(43cm)
タックル
ロッド カーディフ NX S72L
リール ストラディックCI4+C2500HGS
ライン スーパートラウト アドバンス4lb
ルアー MIU4.2g オレ金/金
イイネ!と思ったらポチしてもらえると嬉しいです