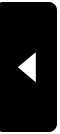シーバスを追い駆けて銚子へ
2018年11月14日
結局、上流部ではろくに釣果が得られないまま、淡水シーバスシーズンは幕を閉じた。
それならば、我が身が下ったシーバスを追うまでである。
少し下流のポイントにいくと、今でもそれなりにシーバスは居る。
ということは、まだ海へは下りきっておらず河口付近に溜まっているに違いない。
そんなアタリを付けて、銚子へと車を走らせる。
まだ明るいうちに到着し、ベイトの様子などを観察したかったので早めに出発した。
しかしまぁ、相変わらず遠い。
満足いく釣果を上げていない今シーズン、そうも言ってはいられない。
コンビニで買ったおにぎりをぱくつき、去年ランカーを上げたポイントへと行ってみる。
ベイトは上ずってはいないものの、時折イナッコが跳ね、水中を覗き込めばヒラを打つ銀鱗の輝きが見える。
シーバスの餌になる魚は豊富である。
しかし、風が強い。
水面がさざ波立つ程の風が吹いており、それがどのように作用してくるかが気がかりである。
陽が傾き、餌釣りの人たちが続々と撤収を始める中、一人タックルの準備に取り掛かる。
やがて陽は暮れ、周辺は貸し切り状態となった。
しかし、ライズは起こらず、捕食音も聞こえてこない。
これは厳しいかな、と思いつつ、キャストを開始する。
時折、イナッコがさざ波立ったり、跳ねたりするので完全に捕食者が居ないわけではなさそうである。
レンジは中層辺りと予想を付け、まずはシンキングミノーから。
レンジを刻みながプレッシャーを与えないようにスローで丁寧に探ってゆく。
すると、中層より若干ボトム寄りでバイトがあった。
それほど大きさを感じないファイトではあるものの、久しぶりのシーバスに胸が高鳴る。
おとなしくなったところで、ネットをするすると堤防下へ伸ばし、キャッチ。
50cm位のシーバスが上がってきた。

引き続き先程同様のレンジを攻めてゆく。
ゆっくりゆっくり、ルアーのアクションを感じないほどのデッドスローでヒットレンジを舐めるようにトレースしてゆく。
堤防下のブレイクに沿うようにルアーを浮かせた瞬間、またもやバイト。
幸先の良い出だしに気分は上々である。
鼻歌交じりにドラグを調節し、ファイトしていると違和感を感じる。
あ、これシーバスじゃない。
水面に顔を出したのは、なかなかのサイズのヒラメであった。

ちなみにこのルアー、タックルハウスのBKS90である。
20年以上前、私がまだ学生だった頃に購入した1本。
シーバス釣りを始めて間もない頃、ルアーの使い方どころかキャストすらままならなかったあの頃。
初心者の私に初めてシーバスという魚を釣らせてくれたルアーである。
タックルボックスで眠っていたこのBKSを見ていると、たくさんの思い出が燦然と蘇ってくる。
手にとって傾けると、磁石がダメになっているようで、コトッと中のウエイトボールが転がる音がした。
「また、連れて行ってくれるのか?」
その音が、こいつがそう呟いているかのように聞こえ、目頭が熱くなった。
「そうだな、多忙さに甘え俺も一度は釣りから足が遠のいた身。共に復帰戦といこう!」
そんなやりとりがあったか無かったか定かではないが、20年の時を経て再び相棒と相成ったのである。

やはりタックルハウスのルアーは良い。
私は別にメーカーの回しものでも何でもないが、良いものは何年経っても良いと釣果が証明してくれている。
まるで手足のように自在に操作でき、釣り人の意志の通りに動き、魚に違和感を与えず口を使わせる。
昔はお前に釣らせてもらったが、今ならお前に釣らせてやることができる。
俺も成長しただろう?
そんなことを心の中で語りかけながら、ヒラメの口からフックを外す。
やっと、自分もこのルアーを使うにふさわしいアングラーになれただろうか。
魚をリリースする瞬間、「まだまだだなぁ」と聞こえた気がした。
その後、さらに風が強くなってゆく。
手前のブレイク付近で反応が得られなくなってきたので、チョーサンに換え少し沖にキャストする。
しばらくキャストを続けると、小さなバイトと思われる反応がある。
合わせを入れるも、うまく乗らない。
これは、ミニセイゴの群れが回ってきたかな。
5度目位でやっとフッキングする。
抜きあげてみると、まぁかわいらしいセイゴちゃんであった。

その後もしばらく粘るが、小さなアタリばかりである。
かなり小型の個体が主体の群れが入ってきているようで、次に釣れたのも20cm程のセイゴであった。
釣るのもしのびなく、風も収まる気配が無いのでこれで納竿とした。

シーバスは釣れはしたものの、ベイトの量に対してシーバスが少なすぎる印象を受けた。
ひょっとしたら、まだ海へ下りきってはおらず、河川下流域に大半の個体は溜まっているのかもしれない。
次回は少し上流の気水域を中心に調べてみようかと思う。

結局、上流部ではろくに釣果が得られないまま、淡水シーバスシーズンは幕を閉じた。
それならば、我が身が下ったシーバスを追うまでである。
少し下流のポイントにいくと、今でもそれなりにシーバスは居る。
ということは、まだ海へは下りきっておらず河口付近に溜まっているに違いない。
そんなアタリを付けて、銚子へと車を走らせる。
まだ明るいうちに到着し、ベイトの様子などを観察したかったので早めに出発した。
しかしまぁ、相変わらず遠い。
満足いく釣果を上げていない今シーズン、そうも言ってはいられない。
コンビニで買ったおにぎりをぱくつき、去年ランカーを上げたポイントへと行ってみる。
ベイトは上ずってはいないものの、時折イナッコが跳ね、水中を覗き込めばヒラを打つ銀鱗の輝きが見える。
シーバスの餌になる魚は豊富である。
しかし、風が強い。
水面がさざ波立つ程の風が吹いており、それがどのように作用してくるかが気がかりである。
陽が傾き、餌釣りの人たちが続々と撤収を始める中、一人タックルの準備に取り掛かる。
やがて陽は暮れ、周辺は貸し切り状態となった。
しかし、ライズは起こらず、捕食音も聞こえてこない。
これは厳しいかな、と思いつつ、キャストを開始する。
時折、イナッコがさざ波立ったり、跳ねたりするので完全に捕食者が居ないわけではなさそうである。
レンジは中層辺りと予想を付け、まずはシンキングミノーから。
レンジを刻みながプレッシャーを与えないようにスローで丁寧に探ってゆく。
すると、中層より若干ボトム寄りでバイトがあった。
それほど大きさを感じないファイトではあるものの、久しぶりのシーバスに胸が高鳴る。
おとなしくなったところで、ネットをするすると堤防下へ伸ばし、キャッチ。
50cm位のシーバスが上がってきた。
引き続き先程同様のレンジを攻めてゆく。
ゆっくりゆっくり、ルアーのアクションを感じないほどのデッドスローでヒットレンジを舐めるようにトレースしてゆく。
堤防下のブレイクに沿うようにルアーを浮かせた瞬間、またもやバイト。
幸先の良い出だしに気分は上々である。
鼻歌交じりにドラグを調節し、ファイトしていると違和感を感じる。
あ、これシーバスじゃない。
水面に顔を出したのは、なかなかのサイズのヒラメであった。
ちなみにこのルアー、タックルハウスのBKS90である。
20年以上前、私がまだ学生だった頃に購入した1本。
シーバス釣りを始めて間もない頃、ルアーの使い方どころかキャストすらままならなかったあの頃。
初心者の私に初めてシーバスという魚を釣らせてくれたルアーである。
タックルボックスで眠っていたこのBKSを見ていると、たくさんの思い出が燦然と蘇ってくる。
手にとって傾けると、磁石がダメになっているようで、コトッと中のウエイトボールが転がる音がした。
「また、連れて行ってくれるのか?」
その音が、こいつがそう呟いているかのように聞こえ、目頭が熱くなった。
「そうだな、多忙さに甘え俺も一度は釣りから足が遠のいた身。共に復帰戦といこう!」
そんなやりとりがあったか無かったか定かではないが、20年の時を経て再び相棒と相成ったのである。
やはりタックルハウスのルアーは良い。
私は別にメーカーの回しものでも何でもないが、良いものは何年経っても良いと釣果が証明してくれている。
まるで手足のように自在に操作でき、釣り人の意志の通りに動き、魚に違和感を与えず口を使わせる。
昔はお前に釣らせてもらったが、今ならお前に釣らせてやることができる。
俺も成長しただろう?
そんなことを心の中で語りかけながら、ヒラメの口からフックを外す。
やっと、自分もこのルアーを使うにふさわしいアングラーになれただろうか。
魚をリリースする瞬間、「まだまだだなぁ」と聞こえた気がした。
その後、さらに風が強くなってゆく。
手前のブレイク付近で反応が得られなくなってきたので、チョーサンに換え少し沖にキャストする。
しばらくキャストを続けると、小さなバイトと思われる反応がある。
合わせを入れるも、うまく乗らない。
これは、ミニセイゴの群れが回ってきたかな。
5度目位でやっとフッキングする。
抜きあげてみると、まぁかわいらしいセイゴちゃんであった。
その後もしばらく粘るが、小さなアタリばかりである。
かなり小型の個体が主体の群れが入ってきているようで、次に釣れたのも20cm程のセイゴであった。
釣るのもしのびなく、風も収まる気配が無いのでこれで納竿とした。
シーバスは釣れはしたものの、ベイトの量に対してシーバスが少なすぎる印象を受けた。
ひょっとしたら、まだ海へ下りきってはおらず、河川下流域に大半の個体は溜まっているのかもしれない。
次回は少し上流の気水域を中心に調べてみようかと思う。